孤独な青い瞳

(提供:腐男子)
第1章:孤独な青い瞳
放課後の教室は、昼間の喧騒が嘘のように静まり返っていた。薄暗い窓の外には、灰色の雲が低く垂れこめ、冷たい風が廊下の隙間から忍び込む。僕、ゆいは、机の隅で肩を小さく震わせていた。
「帰らなきゃ……帰らなきゃ……」
呟く声は震え、ほとんど聞こえない。僕の手足は冷たく、そこかしこに青黒い痣が広がっている。制服の袖で隠そうとしても隠しきれず、見るたびに胸が締めつけられた。
この場所にいても、家にいても、僕を守ってくれる人はいない。孤独がどんどん心を蝕んでいく。
そんな僕の前に、冷たい青い瞳がゆっくりと降りてきた。
「音羽……」
名前を呼ぶと、彼は言葉を返さず、静かに僕を見下ろした。透き通るような白い肌、白銀の髪、その青い瞳は獲物を見つめる捕食者のように冷たかった。
「お願い、放して……帰りたいんだ」
僕の声は震え、切実だった。しかし、音羽は無言で近づき、手枷を取り出して僕の手を掴み、容赦なくはめていった。
「やめて……やめてよ!」
必死に抵抗しても、彼は冷酷で無言のままだった。続けて足枷が取り付けられ、僕の体は次第に動かなくなっていく。
「音羽、お願い、放して……」
涙がこぼれそうになる声で懇願しても、彼は首輪を取り出して僕の首に押し当てた。金属が冷たかった。
「いやだ……そんなの、いやだよ……」
叫びながら逃げ出そうとしても、音羽の手に捕まれてしまう。彼の青い瞳に見つめられ、僕は深く、深く堕ちていくのだった。
教室の冷え切った空気がゆいの震える体を包み込んでいた。音羽は無言のまま、ゆいの肩に触れ、制服の上着を脱がせる。その冷たさが肌に直に触れ、震えが止まらなかった。
「や、やめて……寒い……」
震える声がか細く漏れた瞬間、音羽はバケツの中の冷水をゆいの頭から一気にかけた。
「ひゃあっ!」
冷水が頭から全身にかかり、凍りつくような感覚が走る。ゆいは咳き込み、震えながらも必死に抵抗を試みた。
「離して……やめて……」
音羽の青い瞳は無情にゆいを見下ろし、その冷酷さは氷のように凍りついていた。
頭から冷水をかけられ、全身が凍りつくような痛みと寒さに震えながらも、ゆいは必死に目を閉じて抵抗を続けていた。だが、音羽の青い瞳は一切の情を見せず、冷徹な支配者のようにゆいを見下ろしていた。
「離して……やめて……お願いだよ」
かすれた声が教室の静寂に響く。ゆいの小さな手は震えながらも音羽の腕を払いのけようとするが、力の差はあまりにも大きい。
無言のまま、音羽はゆいの足元の靴下を引き抜き、冷たい素足を露わにさせる。ゆいの震えは止まらず、痛みと寒さが彼の体を容赦なく蝕んでいく。
その場に閉じ込められたような絶望感に包まれながら、ゆいは抵抗をやめなかった。
第2章:閉ざされた教室の檻
教室の時計の針は、刻一刻と時を刻んでいた。
だが、ゆいにとっては時間の感覚すら失われていた。冷水が頭から全身を打ち、体中を震えが這い回る。靴下を脱がされ、裸足になった足元には手枷と足枷の冷たい鉄が絡みつき、逃げ出すことはおろか、動くことさえ許されなかった。
音羽の青い瞳は変わらず冷たく、言葉はなかった。彼の無言の支配にゆいは深い絶望を味わいながらも、心の奥底で何かが生きていた。
「どうして、こんなことを……」
呟く声は震え、震撼した体からは白い息が立ち上る。音羽の心は傷だらけで、誰かに守られたいと願う一方で、自分が無力であることに苛立ちを募らせていた。
「……」
音羽は沈黙のまま、ゆいの髪を指で撫でる仕草を見せた。それは冷たく、優しさとは程遠い、支配の証だった。
「俺のものだ、逃げられない」
言葉はないが、彼の意思ははっきりと伝わる。ゆいの身体を押さえつける圧力と共に、精神をも締め付けていった。ゆいは、身体を小さく震わせながら必死に腕を振りほどこうとした。
手枷と足枷は重く、逃げることなど到底かなわない。それでも足をばたつかせ、弱々しい声で叫ぶ。
「やめて……離して……お願いだよ、音羽……!」
声は必死さを帯びていたが、奥底にあるのは空虚な響きだった。自分の言葉が届かないことは、もうとうに知っている。叫ぶことが意味を持たないことも、分かっている。それでも叫び、抵抗しなければ、自分が完全に壊れてしまいそうだった。
「……っ……」
音羽の青い瞳がゆいを射抜くように見下ろす。その瞳には冷たさと同時に、何か不可解な感情が潜んでいた。ゆいは視線を逸らし、うつむいた。心臓が凍りつくような恐怖を感じながらも、心の奥底で小さく呟く。
(もう、どうせ逃げられない……)
抵抗の動きはまだ続いている。足をばたつかせ、手を振り払う仕草をやめない。けれど、それは希望からではなく、自分がまだ生きている証を示すための弱々しい反射に過ぎなかった。
「……」
涙が頬を伝い、冷たい床に落ちる。ゆいの目は音羽を見上げながらも、すでに遠くを見ているようだった。
第3章:崩れゆく心
ゆいは手枷と足枷に縛られたまま、音羽の青い瞳に見つめられていた。必死に抵抗しているように見えるけれど、その声にはもうどこか諦めが混じっていた。
「やめて……お願い……」
かすれた声は震え、体は冷たく硬直している。音羽は言葉を発さず、ゆいの動きを静かに封じ込めた。寒さと痛みがゆいの全身を蝕み、彼の心は次第に凍りついていく。けれど、ゆいの中にはまだ小さな炎が灯っていた。それは、どんなに薄くても、消えないでいる。
「……まだ、終わってないんだ」
ゆいは目を閉じて、過去の記憶を思い出そうとした。守られたかった日々、友達の笑顔、少しだけ輝いていた未来の欠片。
だが、音羽の無言の支配は、そんな希望すら飲み込んでいった。
教室の冷たい空気が身体の隅々まで染み込んでいく。冬の凍える風が窓の外で唸りをあげ、薄暗い照明が陰を落としたその場所で、ゆいは手枷と足枷に縛られながらも、必死に抗っていた。だが、抗う力は日に日に削られ、心はどこか遠くへと逃げていく。
震える指先で、ゆいは自分の腕を必死に引き裂こうとした。自由を求めるその小さな動きは、かつての自分の強さの証だったはずだ。しかし、その手は音羽の手によって強く握られ、動きを封じられた。
音羽はほとんど言葉を発さず、その冷たい瞳でただゆいを見下ろすだけだった。その沈黙が一層の恐怖を生み出し、ゆいの心の中にぽっかりと穴を開けていく。
「まだ、ここで終わりたくない……」
心の奥底でつぶやいた言葉は、外には決して出なかった。叫びたい気持ちもあったが、声は震え、喉は詰まったままだった。身体の痛みも、冷たさも、どれもが彼を押しつぶそうとする重圧だった。
それでも、ほんのわずかな希望が彼の中に残っていた。いつかこの閉ざされた檻から抜け出し、音羽の支配から逃れられる日が来ることを願いながら。
だが、その日が訪れるのはまだ遠い先のことのように思えた。
冬の夕暮れ、窓の外は白い吐息のような冷たい風で覆われていた。教室の蛍光灯がちらちらと点滅し、ゆいの顔に陰影を落とす。
手首には重たい手枷、足首にも冷たい鉄の感触。逃げるという選択肢はとうに消え去っていた。それでもゆいは、震える唇をかすかに動かした。
「……わかった、音羽。言うとおりにする」
その言葉を口にした瞬間、胸の奥で小さな何かが崩れる音がした。抵抗しようとする気持ちはもうほとんど残っていない。だが、心のどこかでまだ叫んでいる自分がいた。
音羽は、無言でゆいを見下ろし、青い瞳でその奥底まで覗き込む。言葉ひとつ発さないのに、その視線だけで「命令」が伝わってくるようだった。
ゆいは頷いた。頷くしかなかった。拒絶の仕草を見せるたびに、音羽の手が強く肩に置かれる。その冷たい圧力は、言葉以上に「逃げられない」という現実を刻みつけた。
「……っ」
声にならない声が喉で詰まり、涙が滲む。心の奥底では諦めと恐怖が混ざり合い、ゆいの心を真っ黒に染めていった。
第4章:沈黙の中で
教室に流れる冷たい空気の中、ゆいはもう動かなかった。手枷も足枷も重いのに、今はその重さすら感じない。必死に逃げようとしていた足も、叫び続けた声も、全部どこか遠くに消えてしまった。
「……」
音羽の青い瞳がゆいを見下ろす。何も言わないその瞳に、ゆいは自分の姿が映っていないことを知っていた。
「……何もしない。……もうなにもしないよ」
その声はあまりに小さく、諦めきった囁きのようだった。抵抗の動きは完全に止まり、ゆいの体はただ音羽の意のままに動かされるだけになっていた。冷たい床に膝をつき、ゆいは目を閉じる。
自分が“誰か”だったことを思い出せないまま、音羽の支配の中に沈んでいく。窓の外は灰色の空が広がり、校庭には誰の気配もない。冷たい風が隙間から吹き込み、教室の薄暗い空気をさらに重くする。
ゆいはその冷気を感じながら、ただ静かにそこにいた。かつては何度も叫び、足掻き、腕を振り払おうとした。しかし今は、何もしていない。自分の声も、手足の感覚も、他人を見ているような感覚だった。
「……」
音羽の青い瞳がゆいの瞳に映る。その青は氷のように冷たく、しかしどこか底の見えない暗さを孕んでいた。ゆいはその瞳を見つめ返すこともせず、ゆっくりと目を伏せる。
「もう……何もしないから…」
かすかな声は、諦めとも受容ともつかない響きだった。その言葉に音羽は何も答えない。ただ静かにゆいを見ているだけだ。無言の支配。沈黙の命令。それに従うことでしか、自分を保てない現実。抵抗をやめるというのは、負けることではない。それはただ、生き延びるための最後の手段だった。
窓の外に白い息が流れていく。ゆいの視界はぼやけ、時間の感覚が薄れていく中で、音羽の影だけが静かにそこにあった。
第5章:凍った過去
あの日の放課後、初めて音羽を見たとき、ゆいは自分でも説明のつかない恐怖と安堵の両方を感じた。白銀の髪、透き通るような青い瞳、そしてどこか現実離れした冷たさ——それはまるで冬の氷柱のようだった。音羽は、学校の中でも常にひとりだった。教室で話しかける人もいない。
教師たちも、彼の無言の視線に触れれば、それ以上踏み込もうとしなかった。だが、ゆいだけは知っている。音羽がなぜそんな冷たい瞳をしているのかを。
——二人は同じ町の孤児院で育った。小さいころから大人たちの目に晒されず、互いの存在だけが支えだった。
音羽は、ゆいがいじめられて泣いているとき、いつも側にいた。その頃の彼は無口ではあっても、決して冷たい人間ではなかった。けれど、時間が経つにつれ、音羽の瞳は変わった。守っていたはずのゆいを、いつの間にか囲い込むようになった。
「守る」という言葉が「支配」に変わっていく過程を、ゆいはずっと近くで見ていた。
「……音羽」
今、目の前にいる彼は、かつての彼ではない。それでも、心のどこかでゆいはあの頃の優しい彼を探している。
だからこそ、逃げられない。だからこそ、抗いきれない。
ゆいの胸の奥で、昔の音羽信じる気持ちが、諦めと依存の狭間で揺れている。それが、ゆいが今ここに縛られている本当の理由だった。
第6章:音羽の影
音羽は生まれつき目立つ存在だった。白銀の髪、青い瞳。その姿は街の子供たちのからかいや偏見を引き寄せ、彼を孤独へと追い込んだ。父親は幼い頃に蒸発し、母親も病弱でいつも部屋の奥に横たわっていた。「普通の家族」というものを、音羽は知らなかった。
孤児院に引き取られたとき、すでに音羽は誰にも心を開かない子供だった。黙って耐え、誰にも触れられない世界の中で、ただ一人、ゆいだけが彼に話しかけた。泣き虫で、黒髪を垂らして、いつも怯えているその少年は、音羽にとって初めて「守らなければならない存在」になった。だが、その感情は音羽にとって未知のものだった。
守る、愛する、失わないためにどうするか、を知らない彼は、いつしか“囲い込む”ことでしか安心を得られなくなっていった。
「お前だけは、俺のそばにいろ」
その言葉は小さな頃、震える声でつぶやいた“お願い”だった。けれど今は、命令の形でしか口にできない。音羽自身も、どこで線を越えたのか分からないままだった。
孤児院を出て高校に入ってから、音羽の世界はさらに閉じていった。周囲との壁は厚くなり、ゆい以外の存在はどんどん遠ざかっていった。気づけば、ゆいを「守る」ことが「支配」になり、彼はその支配の中でしか自分を確かめられなくなっていた。
青い瞳に映るゆいの姿だけが、音羽の世界のすべてだった。けれど、その視線の奥には、幼い頃のあの孤独と恐怖が今も残っている。それを誰にも知られず、抱えたまま、音羽はゆいを失わないために手を伸ばし続けている。
第7章:心の奥の揺らぎ
冷たい教室の隅で、ゆいは音羽の青い瞳を見つめていた。その瞳の奥に、かつて自分が知っていた少年の影がほんの一瞬、見えたような気がした。
(……音羽も、あの時の僕と同じだったんだ)
孤児院での記憶が蘇る。吹き溜まりのような生活の中で、いつも一人ぼっちだった音羽。あのとき自分を庇ってくれた音羽の姿。ゆいの胸に、もうひとつの感情が芽生え始める。
(怖い。でも……悲しい)
これまでのゆいはただ恐れ、逃げようとし、諦めようとしていた。しかし今、目の前にいる音羽は「ただの支配者」ではなく、誰にも救われず、ひとりで凍えてきた“あの音羽”のままなのだと気づきかけていた。
「……音羽、どうして、こんなふうになったの」
その言葉は、かつての抵抗の声とは違う、問いかけだった。音羽は何も言わない。ただその青い瞳が微かに揺れる。ゆいはその揺らぎを見逃さなかった。
自分の中の恐怖と憎しみと諦めが、ゆっくりと形を変えていく。それは許しではなく、理解に近いもの。しかしその理解は同時に、ゆいを新たな決断へと導こうとしていた。
(このまま音羽のものになって壊れるか、それとも、この鎖を断ち切って音羽を救うか……)
ゆいの心は、静かに変わり始めていた。青い瞳と黒い瞳が交わるその瞬間、二人の物語がほんの少しだけ違う方向に動き出した。
第8章:凍てつく楽園
冬の夕暮れ、窓の外では雪が降り始めていた。白い粒が闇に吸い込まれていくのを見つめながら、ゆいは思った。
(もう、逃げることはできない……そして、逃げたくない)
恐怖と諦めの中で、それでもゆいは音羽の奥底にある孤独を見つけてしまった。彼の青い瞳の奥には、子供の頃の音羽の影がまだ生きている。その影は、ゆいが持つ孤独とよく似ていた。
「……音羽」
ゆいはそっと名前を呼ぶ。その声には、恐怖も怒りもない。ただ、深い諦めと、寄り添うような響きがあった。音羽は言葉を発さず、ゆいを見下ろしていた。その青い瞳がわずかに揺れた瞬間、ゆいはその手に自分から触れた。
もう抵抗しない、ただし、従うだけでもない。同じ深淵へ、自分から降りていくような感覚だった。
(これで、音羽は孤独じゃなくなる……俺も、もうひとりじゃない……)
その考えが正しいのかどうか、ゆいには分からなかった。けれど、あの寒い孤児院の夜に二人で交わした約束
——「お前だけは、俺が守る」——
その言葉の重さだけが、今は胸に残っていた。外の雪はますます激しくなり、音もなく降り積もっていく。その中で、二人の世界は誰にも届かない場所へ沈んでいった。
最終章:雪の白と二つの影
雪は止むことを知らなかった。校舎のガラスに吹き付けられた白い結晶は、外の景色をぼやけさせ、世界を段々と音を失わせる。教室の蛍光灯はちらつき、小さな冷気が窓枠から入り込んでいた。外界と隔絶されたその空間は、いつの間にか二人だけの領域になっていた。
ゆいは窓際の席に座り込んだまま、膝の上で唇を噛んでいた。手首の跡も、痣も、もう数えることすらしなくなっている。彼にとって痛みはもはや外界の合図ではなく、日常の一部になっていた。体が覚えた痛みと冷たさが、記憶の端を剥がしていく。
「音羽」
ゆいは小さく囁いた。呼びかけはもはや懇願でも非難でもなく、ただ事実を確認するための言葉だった。自分はここにいる、あの人はそこにいる——それだけを確かめるための静かな合図。
音羽は教室の中央に立ち、窓の外の白さを見つめていた。白銀の髪に雪の欠片が薄く溶けている。彼の青い瞳は深く澄んでいたが、その奥は凍りついていて、感情が表面に立ち上ることは稀になっていた。ゆいは、その瞳のどこかにかつて自分が知っていた温もりを探したが、見つからないことを知っていた。
「もう、疲れた」─ゆいの声はどこか遠いところから来ていた。
「……そうだな」─音羽は静かに頷いた。
言葉は少ない。二人に残された言葉は、いつの間にか簡素で、重荷を軽くするものではなく、ただ状況を示すだけのものになっていた。
冬の空気の中で、二人の時間はゆっくりと流れていった。互いの呼吸の音、靴底が床に触れる音、水道の向こうから聞こえるかすかな流れる音──わずかなものだけが、二人を現実に繋ぎとめていた。だが、その紐も細く擦り切れかけている。
ゆいは立ち上がると、音羽の方へゆっくり歩いて行った。手は震え、呼吸は浅い。いつものように抵抗するでもなく、だが従属的でもない、微妙な主体性を湛えた歩みだった。彼は音羽の前に立ち止まり、その瞳をじっと見上げた。視線のやり取りは長かった。そこにあったのは恐怖だけでなく、複雑で深い思いで満ちていた。
「俺たち、ここで終わりにしよう」──ゆいの声はかすかに震えていたが、それは決意の震えでもあった。逃げるための叫びではない。何かを終わらせるための合図だった。
音羽はその言葉を受け止めるように、ゆっくりと手を伸ばした。いつもは冷たいその手が、今はどこか頼りなく、震えているように見えた。二人の指が触れ合った。指先を通じて伝わるのは、所有でも支配でもなく、ただの温もりの残照のようなものだった。
「残しちゃいけないものがある」─音羽の声は低く、重い。
「何を残すの?」─ゆいは問い返す、でも答えはもう決まっている。二人の間には言葉で交わすべき未来は残っていなかった。
教室の外、雪はますます激しく降る。世界は白で満たされていく。外界の騒音はもう聞こえず、時間は二人のためにゆっくりと沈んでいった。
ゆいは音羽の手をしっかりと握りしめた。硬く、冷たいその掌を、自分のものにするように。握り返す力は弱いけれど、確かに二人の意志がそこにあった。支配と服従の構図は逆転することなく、二人はお互いを同じ深みへと誘うように視線で合図を交わす。
音羽は何も言わず、ただゆいの額にそっと触れた。その接触は短く、切実だった。雪の降る夜に、二人は唇を交わすでもなく、抱きしめ合うでもなく、ただそばにいるという行為だけでお互いを確かめ合った。それは愛でも憎しみでもない。むしろ、それらを超えた静かな終焉の儀礼のように見えた。
教室の時計はいつの間にか深夜の針を超えていた。時間の重みが床に沈み、二人は座り込む。外の雪が窓に白く張り付き、世界の縁がぼやけていく。やがて、ゆいは小さな袋を取り出した。中身は静かな決意を示すためのもので、詳細はここに記さない。だが、その動作のひとつひとつが、二人の心の決定を表していた。


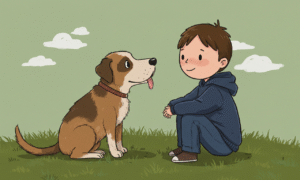

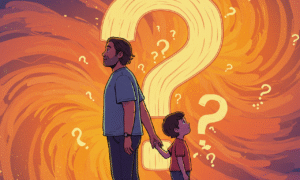




続きを書く